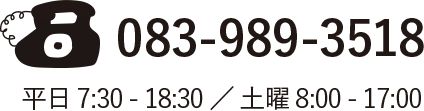スマホと子ども
園長から連日、厳しい暑さが続いていますが、夏の季節も、少しずつ終わりが近づいてきました。9月には、いよいよ大運動会へ向けた練習も始まります。過ごしやすくなっていく季節の中、子ども達の成長がいよいよ楽しみです。
さて、今から4年前に、東北大学の川島隆太教授を中心とする研究グループが、スマホの使用時間が長い子どもの大脳に、発達の遅れが見られることを発表しています。川島教授は、次のように語っておられます。
「平均11歳の子ども223人の脳を3年間モニタリングした結果、スマホを含むネット漬けの子どもほど、思考や創造のほか、人の気持ちを理解したり、場の空気を読んだりするような高次なコミュニケーションをつかさどる前頭前野を中心に、脳が発達していないことがわかりました。記憶や学習に関わる海馬や、言葉に関係する領域などにも影響が見られます。スマホを使っているときは脳があまり活発に動いていないという文献は多く出ていますが、スマホは人間が楽をするための道具ですから、当然といえば当然です。」
日常の中に何気なく潜む危険に、はっとさせられたことでした。子ども時代は、人と人との関わりの中で、大きく脳が発達していく時期です。人の気持ちを理解したり、言葉を使ったコミュニケーションなどの人間らしさが、機械の使用によって奪われていくことは、とても悲しいことです。やっぱり子どもというのは、たくさんの人との関わり合いの中で、たくさん泣いて、たくさん笑って、大人を喜ばせたり、心配させたり、その中でこそ、たくましく成長していけるものなのでしょう。
川島教授は「脳は、悪い習慣を断ち切るだけで、機能が回復することもわかっています。つまり、スマホと上手に付き合えるようになれば、再び発達していきます。」とも語っておられます。子ども達が、機械と上手に付き合えるようになるまで、たくさんの人々や命ある草木や虫、動物たちとの関わりを大切に、泣いたり笑ったりの子ども達の姿を喜べる大人でありたいですね。